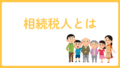相続税の基本をシンプルにご説明します。
相続税では亡くなった方のことを「被相続人」、その方の財産を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。
相続税の対象となるもの
相続税の対象となる財産は、預貯金や有価証券、土地、建物といった明確なものだけでなく、金銭的価値のあるすべてのものが含まれます。なお、相続財産の中には時価が不明確なものもあります。その場合、国税庁が定めている「財産評価基本通達」というルールに基づいて金額を計算します。この算出方法を財産評価と呼びます。
| ■プラスの財産 | 財産の種類 | 内容 |
| 金融資産 | 現金、預金、国債、株式、投資信託など | |
| 不動産 | マンション、家、土地、田畑、山林、借地権など | |
| 動産 | 車、貴金属、宝石、骨とう品、事業用の機械や商品など | |
| その他 | ゴルフ会員権、リゾート会員権など |
■マイナスの財産
マイナスの財産とは、被相続人が遺した債務や、被相続人の葬儀費用を指します。これらのマイナスの財産は、プラスの相続財産から差し引いて相続税額を計算します。この計算を債務控除といいます。
| 債務 | 借入金、未払いのクレジットカード代金、未納の税金、未払いの医療費、その他未精算の費用など |
| 葬儀費用 | 通夜、葬儀、読経料など |
■みなし相続財産
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって取得する生命保険金や死亡退職金などを指します。これらは民法上、受取人固有の財産とされ、被相続人の遺産そのものではありません。しかし、被相続人の死亡という事実に基づいて財産的利益が移転することから、実質的には相続財産と同様の経済的効果があるとみなし、相続税の課税対象とされています。
| 死亡保険金 | 保険料のうち被相続人が負担した部分が対象です。 |
| 死亡退職金 | 死亡後3年以内に支払いが確定したものが対象です。 |
■贈与財産
被相続人から相続人が生前に贈与された財産は、相続税の計算に含める必要がある場合があります。この制度を「生前贈与加算」といいます。
具体的には、相続時精算課税が適用された財産は、贈与時期にかかわらずすべて相続税の計算に含めます。一方、それ以外の一般の贈与については、贈与された時期によって加算対象となるかどうかが決まります。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
| ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって 3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって 7年前の日から死亡の日までの間) |
■非課税財産
相続税の課税対象とならない財産を「非課税財産」といいます。
| 日常礼拝用のもの | 墓地、墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常的に礼拝に使われるもの。ただし、純金の仏像など投資対象となるものは課税されます。 |
| 公益目的の寄付 | 宗教、慈善、学術などの公益事業に使う財産。 |
| 心身障害者共済制度からの給付金 | 心身障害者共済制度から支給される給付金。 |
| 非課税枠内の生命保険金 | 「500万円 × 法定相続人の数」までの部分。 |
| 非課税枠内の死亡退職金 | 「500万円 × 法定相続人の数」までの部分。 |
| 特定の幼稚園事業用財産 | 個人経営の幼稚園事業に使われていた財産で要件を満たすもの。 |
| 国・地方公共団体等への寄付 | 相続税申告期限までに国、地方公共団体、または特定の公益法人等に寄付したもの。 |